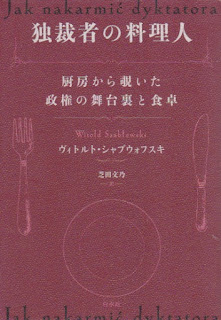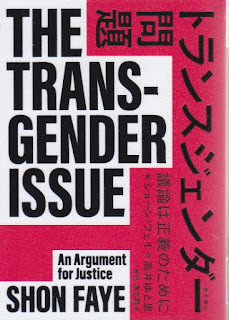ローレンツ・イェーガー『ハーケンクロイツの文化史』に、詞の一部が引用されていた。すぐにYouTubeで探して聴いてみた。
VIDEO
ローリング・ストーンズの傑作のひとつ『悪魔を憐れむ歌-Sympathy For The Devil』だ。
ミック・ジャガーの歌声も魅力的だが、詞の良さに唸ってしまった。これは訳すしかない。
Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long years
Stole many a man's soul and faith
And I was 'round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate
Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game
I stuck around St. Petersburg
When I saw it was a time for a change
Killed the czar and his ministers
Anastasia screamed in vain
I rode a tank
Held a general's rank
When the blitzkrieg raged
And the bodies stank
Pleased to meet you
Hope you guess my name, oh yeah
Ah, what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah
(woo woo, woo woo)
I watched with glee
While your kings and queens
Fought for ten decades
For the gods they made
(woo woo, woo woo)
I shouted out,
"Who killed the Kennedys?"
When after all
It was you and me
(who who, who who)
Let me please introduce myself
I'm a man of wealth and taste
And I laid traps for troubadours
Who get killed before they reached Bombay
(woo woo, who who)
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
(who who)
But what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby
(who who, who who)
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what's confusing you
Is just the nature of my game
(woo woo, who who)
Just as every cop is a criminal
And all the sinners saints
As heads is tails
Just call me Lucifer
'Cause I'm in need of some restraint
(who who, who who)
So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy, and some taste
(woo woo)
Use all your well-learned politesse
Or I'll lay your soul to waste, um yeah
(woo woo, woo woo)
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, um yeah
(who who)
But what's puzzling you
Is the nature of my game, um mean it, get down
(woo woo, woo woo)
詞を作ったのは、ミック・ジャガーとキース・リチャードとクレジットされている。これには諸説あるようだがここではクレジット通りにしておく。
ちょいと自己紹介させてください
このわたし ちょいと裕福な趣味人でして
ずっとずっと昔から あちらこちらに顔を出しては
そりゃもう多くの人間から魂と信仰を盗んでまいりました
あのジーザス・クライストが
疑いに苛まれたときも そこらにおりました
きっちり仕組んで あのピラトのやつには
きっぱり手を洗わせ しかるべき運命をたどらせてやりました
お会いできてうれしいですよ
我が名に見当をつけていただければよいのですが
ただ あなたがたを悩ませてしまうのは
わたしの仕事がらでして どうかご容赦を
サンクト・ペテルブルクにもしばらくおりました
ちょうど時代は変化を求めておりましたから
皇帝(ツァーリ)とその大臣どもを殺してやりましたら
アナスタシアには悲鳴をあげられましたね
戦車に乗ったこともあります
わたしは将軍の姿でした
ちょうど電撃戦が激しさを増しており
そこいらの屍体の臭かったですな
お会いできてうれしいですよ
我が名に見当をつけていただければよいのですが
ただ あなたがたを悩ませてしまうのは
わたしの仕事がらでして どうかご容赦を
見ているだけで嬉しかったのは
みなさんの王と女王のお歴々が
100年にわたり争いを繰り広げたときのこと
戦いの大義は自分たちで作りあげた神でしたっけ
わたしはこう叫んだこともあります
「誰がケネディ家を殺したんだ?」
実のところを言えば
あれは あなたがたとわたしでやったことですよね
どうか自己紹介させてください
このわたし ちょっと裕福な趣味人でしてね
ちょいと罠をしかけてやったので あの吟遊詩人たちは
ボンベイに着く前に殺されてしまいました
お会いできてうれしいですよ
我が名に見当をつけていただければよいのですが
(おまえは誰だ)
ただ あなたを悩ませてしまうのは
そういう仕事をしているからなのです
(誰だ 誰だ おまえは誰だ)
ちょうど警官の誰もが犯罪者で
罪人が聖人であるのは
コインの裏表のようなもの
わたしのことはルシファーとお呼びください
少しは節度を持たねばなりませんからね
そんなわけで わたしと会うときは
どうかお手柔らかに
少しばかりの同情とご好意をいただければありがたい
ぜひ ご自慢の礼儀正しさを発揮してくださいよ
さもなくば みなさんの魂を滅ぼしてさしあげましょう
お会いできてうれしいですよ
我が名に見当をつけていただければよいのですが
ただ あなたがたを悩ませてしまうのは
わたしの仕事がらでして どうかご容赦を
ここで言われている悪魔とは誰の事だろう?ふとそれが気になった。
多分、悪魔とは我々自身とその愚かさを指しているのではないか?そんな気がする。