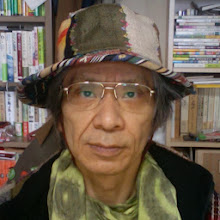記念碑的な論集である。
学部生だった頃、恐竜の研究が、進みつつあるのを、何となく感じていた。だが、その頃は、恐竜の研究に生涯を捧げる者も身近におらず、日本にも、恐竜研究者はさほど誕生していなかった。
その頃と比べると、隔世の感がある。
編者の小林快次さんは、言わば日本の恐竜研究者のスター的存在であり、現在に至る迄、牽引的な役割を一手に引き受けて来た。
この論集が出されたのは、日本人の手による恐竜研究の本が、そろそろ書かれても良い頃だと、感じられたからだと言う。それだけ、日本人の恐竜研究者の裾野が拡がって来ているのだろう。
日本での恐竜発見のニュースも、以前とは段違いに多くなっている。
だが、よもやここ迄研究が進んでいるとは思わなかった。
想像していたより、遙かに定量的、理論的、そして学際的に恐竜研究は進んでいた事を、この論集で思う存分知らされた。
第I部の「進化と歴史」でまず、度肝を抜かれた。
恐竜の分類と進化の過程が、実に詳細に、幅広く述べられているのだ。
恐竜類の系統樹も、詳細に、連続的に描かれていた。
その根拠も、想像していた定性的な推論によるのではなく、定量的、論理的に分類がなされていた。それが分かったのは、再読した後の事で、最初は、図に示された恐竜の種類を追うのに精一杯で、登場する恐竜の多さに溺れていた。
成程なと思わされたのは、鳥類も恐竜の進化と歴史の一部として記載されている事で、考えてみると当たり前の事なのだが、それが当たり前のように書かれている事に、時代を感じてしまった。
恐竜から鳥への進化の過程も、以前は始祖鳥に代表される、点的な描写だった事が、間を埋める標本の発見の充実振りから、線として追跡可能になっており、ひどく驚かされた。
研究の視野は、恐竜の生理・生態から色・姿勢の復元にも及んでおり、それが単なる想像ではなく、幅広い根拠と論理的な類推に裏付けられている事を知った。
それぞれの記載には、現在の研究の到達点と、今後の課題が付せられており、この分野が今後もっと発展してゆくものである事を、実感として理解出来た。
今回は都合3回読破したが、正直言ってまだ十分に理解出来たとは言い難いものを感じている。本来ならば手元に置いておきたい本だが、その資金がないので、今後も折を見て、図書館から借りて読んで行こうと思っている。
その価値が十分過ぎる程ある論集だ。