実はこの本、一度頓挫している。
2年半前に読み始め、1/3くらいで読むのをやめてしまったのだ。
理由は面白くなかったなのだが、他にも私はオーウェルとオーソン・ウェルズを取り違えており、話の脈略が分からなくなってしまった事がある。
オーソン・ウェルズの『市民ケーン』には、薔薇の蕾という「謎の言葉」がある。それが一向に出て来ないのに痺れを切らし、飽きてしまったというのが真相だ。
だが、今回読み始めて、この本がこれ程面白いのか!とびっくりする程だった。驚いたのはそれだけではなく、一度読んだ本ならば、エピソードのひとつくらい覚えているものなのだが、それが全く無かった事がある。
私は何を読んでいたのだろうか?
本書はジョージ・オーウェルの伝記である。と、そう言うのは早合点のようだ。著者レベッカ・ソルニットの断り書きによれば、本書はこれがすでに多く出されているオーウェルの「伝記」の書棚に付け加えられるものではなくて、彼が1936年に薔薇の苗木を自宅に植えたエピソードを「取っ掛かり」とした「一連の介入」だと言う。
確かに、オーウェルから完全に離れてしまうのではないが、関係のない事柄にしばしば話が飛ぶ。
そのような思考のそぞろ歩きを経て、小宇宙のような多彩な拡がりを見せながらも、一冊の本としての統一感は保たれているという、ソルニットの書きぶりの真骨頂がそこにはある。
そのそぞろ歩きは、化石燃料としての石炭(そこから更に脱線して描かれる石炭紀の描写は、並大抵の学習ではここ迄は無理と思われる程見事に纏まっている)と炭鉱労働。帝国主義や社会主義と自然。花と抵抗を巡る考察。現代の薔薇産業などを経て、未来への問いへとつながっている。
薔薇にはどこか特別なところがある。古くから人々を魅了し、多岐にわたる品種改良の歴史を経て世界中で身近な存在であり続けている。
それは文学や絵画音楽などの芸術において繰り返し採り上げられ、時に美そのものの象徴のようにも考えられて来た。
美しいもの、自然であるもの、それらは政治に対して超越的な価値を持つと考えられがちだ。だが本書を通してレベッカ・ソルニットが明らかにしているのは、薔薇は、そして自然は、政治的でもあり得るという事だ。
ソルニットのそうした思索は読者に驚きと衝撃を与えるが、それは同時に解放であり、覚醒でもある。
今まで、レベッカ・ソルニットという書き手は、どちらかと言うと苦手にしてきたが、その苦手意識からも、今回の読書体験で解脱出来た気がする。
今迄読み逃して来たものを、近いうちに再度読み返したい気分に駆られている。

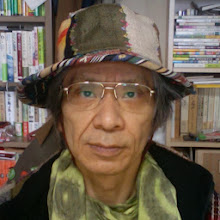

0 件のコメント:
コメントを投稿