腰巻きに「プラトン哲学対話の最高峰!」と謳われている。まだ読んでない。
これは読まねばなるまいと、意を決して読み始めてみた。
老ソクラテスが、10代の天才数学者テアイテトスを相手に、「知識(エピステーメ)」とは何かについて、論じ合った哲学対話だ。
「知識」や「知」については、考えてみると、それが何かは、正面切って考えたことがない。話の流れが、どのようなものになるのか、深い興味を抱いて、本を開いた。
大まかな話の流れは、知識とは何かについて、テアイテトスが仮説を打ち出し、ソクラテスがそれを見事な手捌きで論駁してゆく、そのようなものになる。
途中、ソクラテスの産婆術に関する説明や、プロタゴラスの相対主義の否定など、普通であれば、それだけでも1冊の本に値する大問題が論じられており、その部分も大いに引き寄せられた。
テアイテトスはソクラテスを著名な哲学者として尊敬しており、ソクラテスはテアイテトスを将来有望な若者として認めている。この様な互いに一目置いた同士の議論は、側で聞いていても気持ちが良いものだ。
普段、SNSなどで、議論にもならない議論を読まされている身としては、その事だけでも、新鮮な驚きだった。気分が良くなる議論というものもあるのだ!
テアイテトスが打ち出す仮説も、それなりに説得力を持つ、十分に考え抜かれたものだ。だが、ソクラテスはそれが内に重大な内部矛盾を孕んだものである事を手際よく論じ、論駁して行く。テアイテトスはそれを素直に受け止め、より良い仮説を次々に提出してゆく。その両者の運動は、まさに弁証法そのものであると、私は感じた。
それ故に、両者の対話は結論に至る迄、最終的な解答を得ずに終わるのだが、不思議と取り残され感を感じる事なく、受け止める事が出来た。
本書は、訳も読み易い日本語になっており、注釈も適当に置かれている。更に、本編が終わった後に、訳者解説として、両者の議論を、プラトンの別の著作や、歴史的エピソードに迄守備範囲を広げ、再度確認する事が出来る仕組みになっており、議論の理解をより多面的に理解する事が出来た。
読み終えて、「最高峰!」の掛け声は、伊達ではなく、内容を裏切っておらず、両者の掛け合いを存分に楽しむ事が出来たと感じている。
何よりも、この本は面白い!

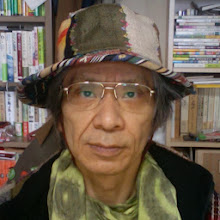

0 件のコメント:
コメントを投稿