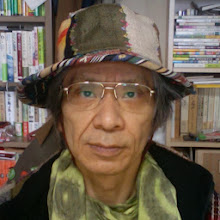月に1冊ずつでも、パレスチナ関係の本を読むようにしている。
それは彼らに加害する西側に属する者として、人間らしく生きる為の一縷の矜持を保とうとする、私の悪足掻きのひとつなのだと思う。
本書『ガザ日記ージェノサイドの記録』は、そんな私の読書歴の中でも、パレスチナの、ガザの現実を、リアルに、そして厳しく突きつけてくる、特別な1冊になった。
著者のアーティフ・アブー・サイフは、ガザ地区のジャバリア難民キャンプ出身の作家で、パレスチナ自治政府の文化相として、通常ヨルダン川西岸地区のラマッラーに住んでいるが、たまたま息子を連れてガザを訪問中にイスラエルの爆撃が始まり、そのまま3ヶ月近くガザに閉じ込められ、親戚や友人たちと共に、ジェノサイドの恐怖を体験することとなった。
本書はその3ヶ月の間の、1日も欠落がない貴重なジェノサイドの記録である。
苦しく、辛い読書になった。
1日分の日記を読む。そこには余りに酷い記述が満ちている。彼等は真に死と隣り合わせに生きている。1日分を読み終える。余りの衝撃に、私は本を閉じる。暫く休む。一日の記載が終わったという事は、著者が眠ったと言う事だ。そして、本が続いていると言う事は、明日があるという事だ。著者と共に、私も休む。読んでいて、2日分の記述を連続して読む事は、遂になかった。
ガザのジェノサイドの犠牲者の数を、私は知っている。そして、その中に子どもの占める数も、また知っている。けれど、それらの人々が、どのような日常(と言って良いのかどうか)を送っているのか、何を体験し、何を感じているのかを知ることは無かった。
それは想像を絶するものだった。
自分が生きているのかどうかが不確かな日常。それはもはや日常とは呼べないだろう。
自分が何かを考えている。だがそれはただ単に、死んでいる事に気付かずに、彷徨っている幽霊の思考なのではないか?その様な疑問を感じざるを得ない状態を、彼等は生きている。
それはつまり、「我思う故に我有り」の、デカルトの「真理」が通用しない日常なのだ。
イスラエルの攻撃に論理はない。動いているものは猫でも狙撃する。
ガザの人々の眠りは、覚醒の保証のない眠りだ。寝ている時に攻撃されたら、永遠に醒める事はない。朝の目覚めは、当たり前の事ではなく、ただ単に良かった運の結果なのだ。
著者は書く。
戦争下では、目覚めてからの数分間がもっとも緊張する。起きるとすぐに携帯電話に手を伸ばし、大切な人たちが誰も死んでいないことを確認する。しかし日が経つにつれ、何を読まされるのか不安になり、携帯電話に手を伸ばすのを躊躇するようになる。携帯電話を手に取る勇気の出ない朝もある。いつかは悪いニュースが飛び込んでくる。
本書を読むのに、結局5日間掛かった。読み終えた瞬間、私は強烈な充実感と無力感という、矛盾した感情に、激しく撃ち倒された。
今、ガザで起きている事は恐ろしい。だが、もっと恐ろしいのは、世界がガザに慣れてしまっているという事だ。