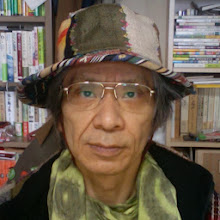行方昭夫氏の編訳による続イギリス・コラム傑作選。続とあるように、正編も存在し、実はそれは本棚にある(これから読もうと思っている)。
正編同様、A.G.ガードナー、E.V.ルーカス、ロバート・リンド、A.A.ミルンの四氏によるエッセイ集だ。
末尾に出典が付されているが、これを読むと、これらのエッセイは2世紀も前に書かれたものである事が分かる。
全く古びていない。まるで今日の人々を観察して書かれたものの様にフレッシュなのだ。
それだけ、エッセイストの人間観察が、その本質をずばりと付いていて、人間というものはその部分で、さほど変化していないのだという事に気付かされる。
その観察眼は人間ばかりではなく、犬や猫などの動物、そしてステッキや傘などの無生物にも及んでいる。
本書では、各エッセイに続いて、編訳者行方昭夫氏の筆による「さらにお許しいただければ」という短い解説が付せられている。読者は各エッセイの見事さに感嘆の声を上げ、それに引き続いて解説で、よりエッセイを深いところで味わえる仕組みになっているのだ。
良いエッセイは美酒に準えられる事が多い。本書は上質なシャンパンの様な爽やかな飲み応えと、程良い酔い心地があり、それぞれの文章を、心地良く味わう事が出来た。
連日、猛暑が続く。強い陽射しに外出もままならず、部屋に閉じ篭もる日々に、有難いエッセイ集を得る事が出来た。
尚、既にお気付きの方も多いだろうが、本書に含まれているA.A.ミルンとは、あの『くまのプーさん』の作者と言った方が、通りが良いと思う。エッセイもモノにしていたとは知らずにいた。