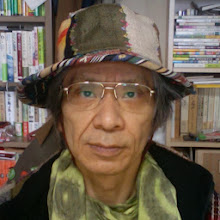難解なヘーゲルの文章を、丁寧に説き起こしてある。なので、例えヘーゲルの訳文が分からなくても、筆者の説明を急がず慌てず読む事で、ヘーゲルを一通り理解する事が可能となっている。
大学時代、とある事情から、ヘーゲルとは壮絶な格闘をして来た。解説書も何冊か読んだ。だが、理解出来たかと言うと、甚だ心許ない。
あの頃の苦労はなんだったのだろうかと、脱力する程、本書が説くヘーゲル像は分かり易かった。
筆者がこの本で言いたい事は、従来のヘーゲル像の解体と新たなヘーゲル像の建設であると言う事が出来ると思う。
従来はヘーゲルと言えばまず弁証法であり、ヘーゲルは西洋近代哲学を完成させた偉大な哲学者だった。だが筆者はそれを、古い硬直化したヘーゲル像であると主張する。
それならば、それに代わる新しいヘーゲル像とは何かが求められる。
筆者はそれを「流動性」にあるとしている。
本書はその「ヘーゲル哲学の流動性」の感覚を掴むために、『精神現象学』と『大論理学』を例に、ヘーゲル哲学を理解するための「取っかかり」を提示して行く。
正直言って、従来より遥かに分かり易いとは言っても、対象はヘーゲルである。難しかった。だが、引用してあるヘーゲルの言説は、筆者が原文から独自に訳出したものであり、頻繁に、原語のドイツ語まで遡って説明してあるのが、とてもわかり易く、ありがたかった。大学時代悩んだ「定立」という語の意味を、今回初めて腑に落ちる形で理解する事が出来た。
だが、従来格闘して来た過去のヘーゲル理解が邪魔をして、新しいヘーゲル像に切り替えて行く事がなかなか出来ず、本書を読み解くのに時間を要した。
従来の正反合の硬直化した弁証法の理解から、それを流動と捉える新しい見方への切り替えも、なかなかスムーズに行うことが出来なかった。
本書は、余計なヘーゲル理解の邪魔が入らない、まっさらのヘーゲル初心者の方が、理解し易いのではないだろうか?
だが、筆者の行なっている、ヘーゲルの文章のパラフレーズの仕方は、何とか身に付ける事が出来たように思う。
大学を卒業してから、過去のヘーゲルとの格闘の苦しさの記憶から、ヘーゲルを避けに避けて来たが、今ならヘーゲルの文章を読み解く事が出来そうな気分になっている。
ヘーゲルという岳にも、また登ってみなければなるまい。