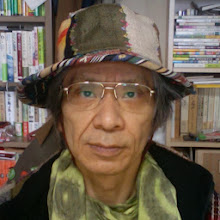還元主義が大流行りである。
人間を含めた生物の事であれば、遺伝子か脳に還元すれば型が付く。そうした論調が、世の中に溢れ返っている。
正直に告白すると、私も一時そうした時勢に相乗りしようとした事もある。だが、そうした考え方で物事を割り切って行くと、どこか心に隙間風が吹く。
どうしても何か見落としている感覚が残り、強烈な違和感に襲われて来た。
だが、それをどの様に表現したら良いのか分からないまま、漫然と過ごして来た。
そんな折、この本に出逢った。
この本は『なぜ世界は存在しないのか』と『思考の意味』に挟まれた、マルクス・ガブリエルの3部作の真ん中に当たる。
「私」という現象は、全てが脳に還元出来るものではないことを、理論的に説いている。
読者としては、一般の人々を想定しているらしく、書き方の手付きは柔らかく、ジャーゴンを用いた場合は必ずその解説を付けるなど、細かな心遣いがなされている。だが、
本書で採用するのは反自然主義の視点です。つまり、存在するすべてのものが実際に科学的に調査可能であるわけでも、物質であるわけでもない、という前提に立っています。
と表明がなされているところなどは、極めて挑戦的な本であるとも言える。
つまりマルクス・ガブリエルは唯物論に反旗を翻しているのだ。
それ故にだろうが、読書メーターなどでは、読む価値がない本と断言しているものもあったが、一読した限りでは、そう目くじらを立てる必要はないと感じた。
本書のクライマックスは、そうした反自然主義の表明にあるのではなく、全てを脳に還元するような見方から脱却することで、私たちはようやく自由や民主主義等の自己決定という精神の自由が擁護されるというところにあると私は思う。
現実的に私などは本書を読むことを通じて、様々な思い込みから解放され、心の有り様がかなり楽になるのを感じた程だ。
何よりも本書は、私が長年感じ続けた違和感に、ようやく言葉を与えてくれた本であると言えると思う。